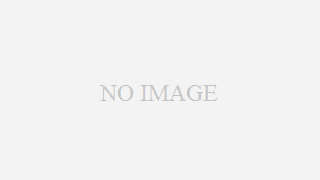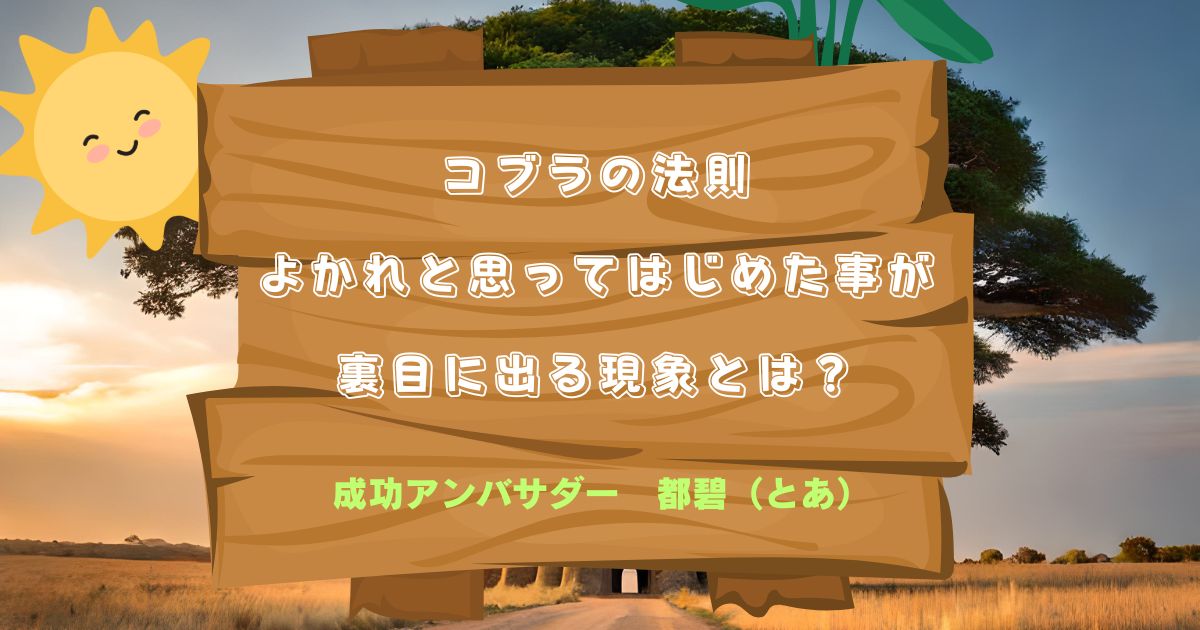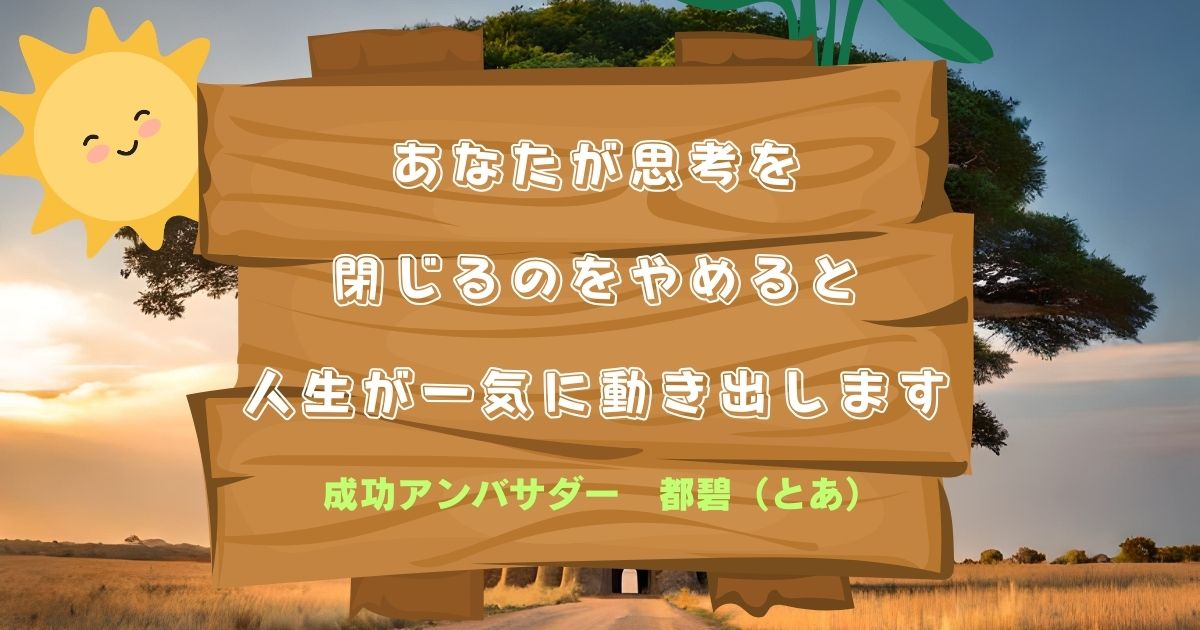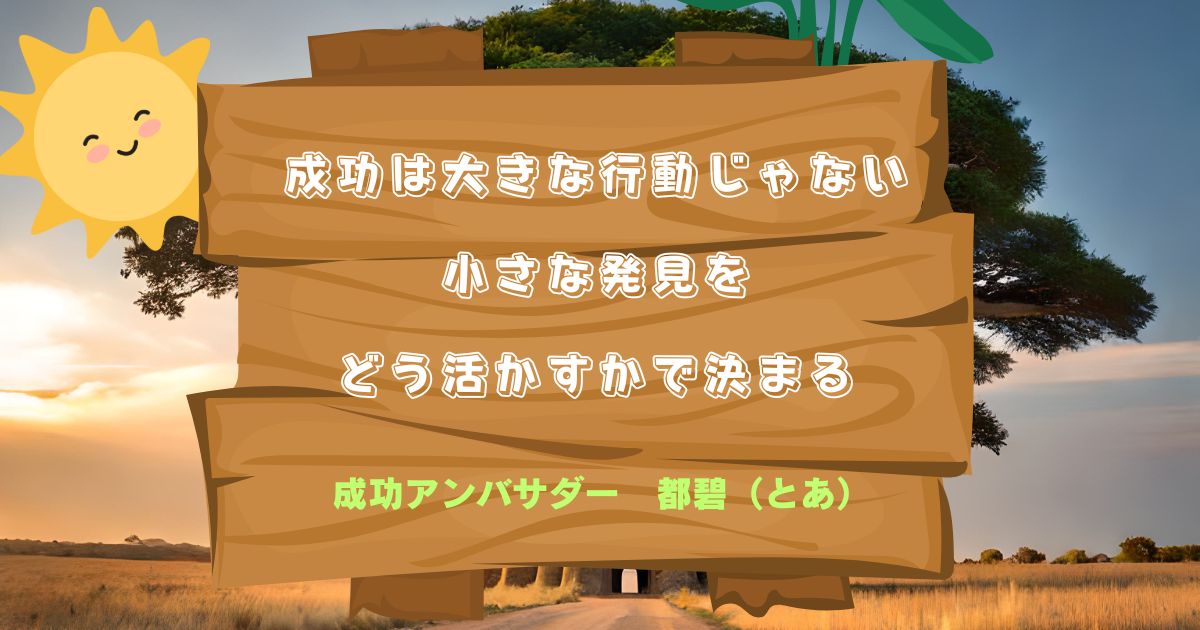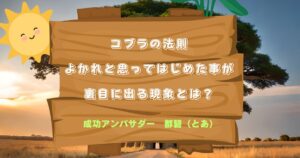
問題や課題を解決しようとしたのに
かえって状況が悪化させてしまった
なんて経験ありませんか?
このような経験は、誰にもあるものです。
それはもしかすると
「コブラの法則(Cobra Effect)」が
働いていたのかもしれません。
この法則は、意図した成果とは
逆の結果を引き起こす
政策や施策の副作用を表したものです。
コブラの法則とは何か?
なぜ起きるのか?
そしてビジネスや日常生活において
私たちがこの法則をどう立ち向かうべきかを
具体例を交えて解説します。
コブラの法則とは?
そもそも「コブラの法則」とは
何かを知らないと話になりませんよね。
コブラの法則(The Cobra Effect)とは
あなたの抱える
問題や課題を解決するために
行った行動が、裏目にでて
逆にその問題を悪化させてしまう
現象のことをいいます。
この名前の由来は
イギリス統治時代のインドで
実際に起きたエピソードからきています。
インド・デリーで起きた「コブラ報奨金制度」
「コブラの法則」の由来は
当時、インド・デリーでは
コブラによる被害が深刻化していました。
そこで当時支配していたイギリス政府は
害を及ぼすコブラを捕獲して
「殺したコブラ1匹につき報奨金を支払う」
という制度を導入しました。
一見、合理的な政策に思えますよね?
実際、最初は効果抜群の結果が現れました。
多くの人がコブラを殺して報奨金を
得ようとしたから現象に向かいました。
ところが、その後に問題が発生します。
ある時を堺にコブラが増えはじめたのです。
それは報奨金目的の人が
コブラを“繁殖”させ始めたからです。
最終的に政府はこの制度を廃止しましたが
その途端、繁殖されていたコブラたちが
野に放たれ、以前よりも深刻なコブラ被害が
発生してしまったのです。
この話に由来するものが
「コブラの法則」と呼ばれるものです。
類似するケース:「ラット報奨金」と「ビールの瓶」
コブラの法則は、他の国でも
似たような例が報告されています。
◆ベトナムでのラット対策
フランス統治下のハノイでは
ネズミ駆除のために
「ネズミのしっぽ1本につき報酬を支払う」
という制度を導入しました。
ところが人々は、ネズミを殺さずに
しっぽだけを切って放し
また繁殖させて再利用するという
行為に走ったのです。
◆ドイツのビール瓶政策
ドイツではリサイクル促進のため
ビール瓶を返却すれば
デポジットが返ってくるという
制度がありました。
しかし、瓶の供給が増えすぎてしまい
空瓶の偽造や、密輸まで
発生するという事態がおこりました。
そのように、様々な場所
最初の目的とは違った結果が
生まれる場合もあるのです。
ビジネスの世界でも起きる「コブラの法則」
コブラの法則は、国家レベルの政策に限らず
企業や組織の日常的なマネジメントにも
起きうる問題もあります。
◆カスタマー対応の「時間短縮KPI」
あるコールセンターでは
「1件あたりの対応時間を短縮すること」が
KPIに設定されました。
すると、スタッフは質より量を優先し
顧客対応が雑になったり
すぐに電話を切るといった問題が起き
顧客満足度が大幅に低下という形で現れました。
問題を解決しようとした施策が
かえって信頼を損なう結果につながってた例です。。
◆社員の成果主義ボーナス制度
売上向上のために実力評価制を
取り入れた時に起こったケースです
売上に応じてインセンティブを出す制度を
導入した企業がありました。
すると、目先のボーナスを優先することに
重きを置いために
社員が無理な契約を取るようになったり
短期的な数字だけを追う行動をとる
ケースがあります。
すると、これにより
顧客との関係が悪化し
長期的な信頼が損なわれるという
悪い「副作用」が起きたりするのです。
なぜコブラの法則は起きるのか?
でも、最初は、よかれと思って
実施したものが結果的に悪い方向へ
進むのでしょう?
その原因は次のものが考えられます。
①短絡的な「数値主義」
「見える数字」で評価しようとするあまり
人の行動はその数字を最大化する
方向に偏ります。
その結果、本来の目的が見失われ
抜け道やズルが発生しやすくなるのです。
②人間の創意工夫は“良くも悪くも”働く
人はルールに適応する能力が高い生き物です。
そのため、「どうすれば効率よく得をするか」を
すぐに考えます。
それが悪意でなくても
制度の“裏をかく”ような行動につながるのです。
③現場の実情を無視した制度設計
現場の声を聞かずにトップダウンで
施策を導入すると
実際の運用にそぐわず
形式だけの制度になります。
現場で形骸化したり、逆効果に
なることも多々あります。
コブラの法則を回避するためのヒント
それでは、「コブラの法則」を
回避するには、どうすればいいのでしょう?
① 「数字だけ」で評価しない
KPI = Key Performance Indicator(重要業績評価指標)
や指標は必要ですが
それが目的化しないように注意しましょう。
定性的な評価やフィードバックの
仕組みを取り入れることでバランスが取れます。
② 目的を明確に言語化する
「何のためにこの制度や対策を行うのか?」を
共有することで
手段が目的化するのを防ぎやすくなります。
③ インセンティブ設計は慎重に
報酬や評価制度は
「どんな行動を促すか?」を想像しながら
設計することが大切です。
副作用が起きる可能性を事前に検討しましょう。
④ 現場の声を取り入れる
制度を運用するのは現場の人たちです
現場からのフィードバックループを
設けることで、修正や改善がしやすくなります。
本質を見失わない制度設計を
コブラの法則は
「よかれと思ってやったことが裏目に出る」
という、誰にでも起こりうる典型的な事例です。
特に、目先の数字や短期的な
成果ばかりを重視すると、
来の目的が見えなくなり
望まぬ結果に直結してしまうこともあります。
重要なのは
「この制度は、何のためにあるのか?」
「どんな行動を促すのか?」
を常に問い続けることです。
問題を解決するための取り組みが
新たな問題を生み出さないように
数字の背後にある人間心理や
行動の複雑さを理解しながら
制度や仕組みを丁寧に設計していくことが
コブラの法則を回避する最も有効な方法です。
成功アンバサダー都碧(とあ)