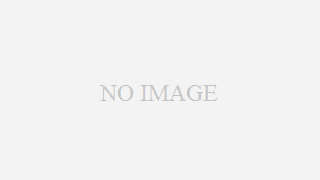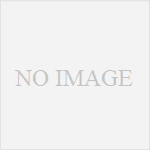あなたの目標が叶う方法は
目標と手段のボタンを掛け違えない
ということです。
「目標を立てたのに、うまくいかない…」
「数字は伸びてるけど
なぜか本質からズレている気がする」
なんて違和感を感じたことはありませんか?
実は、目標に向かって何かのアクションを
しているときに、目標と手段の取り違えという
迷子が、あなたの結果に大きく影響します。
そうならない為に
『グッドハートの法則』をもとに
結果に結びつけるヒントを紹介します。
グッドハートの法則とは?
「指標が目標になると、それは良い指標ではなくなる」
これは、経済学者チャールズ・グッドハートが
1975年に提唱した「グッドハートの法則」です。
英語では
“When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.”
と言われています。
本来「測るための道具」である指標(数値やKPIなど)が
目標になってしまうと、人々はその数字を
上げることばかりに集中し始め
その結果として、いつのまにか
手段と目的が逆転し
数字を追いかけることだけの行動が促され
本来の目的と実態や質が離れていくというものです。
ビジネスや日常で起きている「グッドハートの罠」
具体的にな目的と手段が逆転したものを
見ていくと次のようなものです。
営業のアポ件数至上主義
営業チームで「1日10件のアポを取る」という
目標を設定したとしましょう。
一見すると良い目標に見えますが
実際には、本来営業で大切な「中身のある商談」よりも
「アポ件数をこなすこと」が目的になりがちです。
結果として、アポの数といったものは達成できますが
成約率は下がり顧客との関係も築けず
逆効果になるケースもあります。
テストの点数で評価される教育
今の教育にも同じものが見られます。
「偏差値」や「点数」ばかりに重きを置いた教育では
本来育てたいはずの「思考力」「創造性」「探求心」が
置き去りになります。
これもまた、テストの点数という数字という指標が
「目的化」してしまった例です。
SNSの「いいね」文化
SNSで「いいね数」や「フォロワー数」を
伸ばすことが目的化すると、自己表現ではなく
「バズるための投稿」に偏ってしまいます。
人間関係やメンタルに悪影響を及ぼすことさえあります。
なぜグッドハートの法則が発動するのか?
ではなぜ、このような目的と手段が
逆転することがおきるのでしょう?
1. 数字はわかりやすい
数字は可視化しやすく、比較も容易です。組織運営や評価ではつい頼りたくなります。
2. 評価基準に人は従う
人は「評価される基準」に行動を合わせる傾向があります。
インセンティブが数字に連動すれば
当然、数字ばかりを追いかけるようになります。
3. 本質は測りにくい
「信頼」「誠実さ」「創造力」など
重要な要素ほど数値化が難しいため
測りやすい数字だけが一人歩きしやすくなります。
グッドハートの法則に陥らないための対策
指標は「参考値」であり「目的」ではないと認識する
数字は現状を把握するための「道具」であって
目的そのものではありません
常に、「本来の目的」とのズレを
チェックする視点を持ちましょう。
複数の指標で評価する
営業であれば、アポ数だけでなく
「成約率」「顧客満足度」なども併せて見ることで
より立体的な評価が可能になります。
「なぜそれをするのか?」を定期的に振り返る
数字や目標にとらわれそうになったら
「なぜこの目標を立てたのか?」
「自分たちは何を実現したいのか?」
を言語化しておきましょう。
自分の「軸」を取り戻そう
グッドハートの法則は、「数値化による評価」が
あたりまえになった現代だからこそ
多くの現場で見られる現象です。
重要なのは、「数字を否定すること」ではなく、「数字に支配されないこと」。
自分にとって、チームにとって、本当に大切にしたいことは何か?
それを問い直すことが、グッドハートの罠を避ける第一歩です。
まとめ:数字のその先にある“本質”を見る力を
- グッドハートの法則は、「指標が目標になると、本質を見失う」ことを警告している
- 数字を追いすぎると、質や目的がないがしろになりやすい
- 指標はあくまで道具。目的を定期的に見直し、複数の観点で評価を
- 本質を見失わないことが、真の成果や成長につながる
あなたの現場でも、グッドハートの法則が起きていませんか?
数字や成果に違和感を感じたら、いま一度「目的」を見つめ直してみてください。
本質に立ち返ることで、行動の質が上がり、より深い成果へとつながっていきます。
成功アンバサダー都碧(とあ)